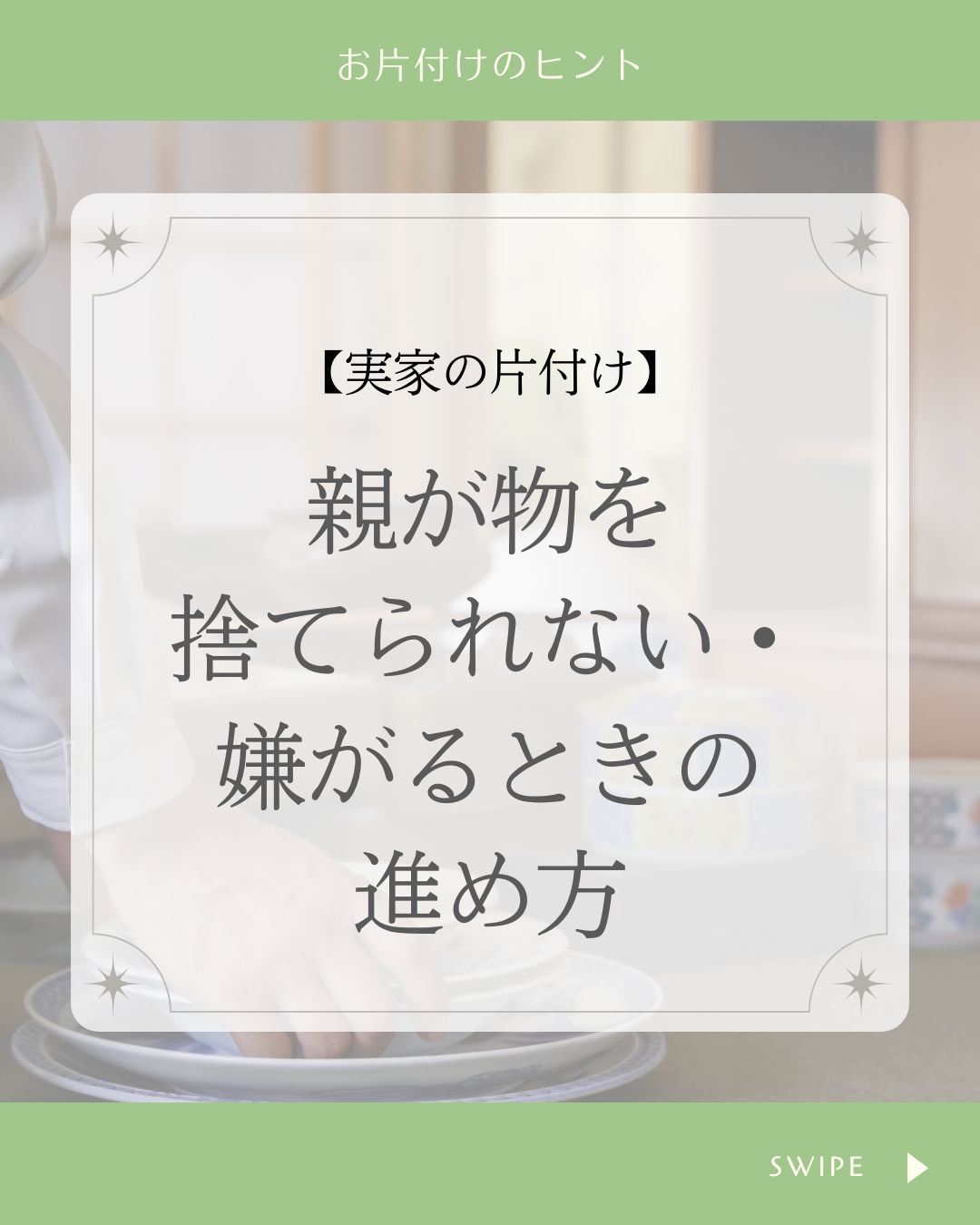お片付けコラム
お片付けコラム · 2025/09/13
実家の片付けをしようとしても「親が物を捨てられない」「片付けを嫌がって拒否される」…そんな悩みを抱える方は多いのではないでしょうか。
そこには世代や心理的な背景があります。
「もったいない意識」「人生を否定されたように感じる」などの理由から、片付けを拒むケースは少なくありません。
この記事では、親が片付けを嫌がる5つの理由と、スムーズに進めるための心がけ、進まないときの工夫を整理収納アドバイザーの視点で解説します。
さらに、第三者が入ることで片付けが一気に進んだ事例も紹介。
実家の片付けに悩む方に役立つ具体的なヒントをまとめました。
お片付けコラム · 2025/07/04
「収納が苦手」「片づけられない」と感じていませんか?物の量はそれほど多くないのに使いにくい、SNSの収納アイデアを真似してもうまくいかない…。その原因は収納センスではなく、実は“整理不足”にあります。収納の本来の目的は「使っているモノを、使いやすく収めること」。そのためには、使っていないモノを整理し、目的や使用頻度でグループ分けし、動線に合わせて配置することが大切です。この記事では収納が苦手な人がやりがちな失敗と、改善のための3つのステップを具体的に解説。整理収納アドバイザーのサポート事例も紹介しながら、「使いやすい収納」に変える実践的なヒントをお届けします。
お片付けコラム · 2025/07/03
「片づけられない」のは、モノが多すぎて管理できなくなっているからかもしれません。
気づいたらモノが増えて収納から溢れてしまう、捨てなきゃと思っても手が止まる…。
そんな悩みは「モノが多すぎるタイプ」によく見られます。
安売りやまとめ買い、ストック癖や趣味のコレクションなどで総量がキャパを超えると、整理できずに探し物や二度買いが増える悪循環に。
この記事では、モノが増える原因と行動パターン、片づけられない人が陥りがちな失敗例を整理収納アドバイザーの視点で解説。
さらに「使っているかどうかで分ける」「適正量を決める」「大切にしたいモノを軸に選ぶ」という3つの視点から、実践できる整理の始め方を紹介します。
増やさない暮らしにシフトして、自分に合った“ちょうどいい量”を見つけましょう。
お片付けコラム · 2025/07/02
「片付けたいのに手放せない」「何を残していいか判断できない」――そんな悩みは、片付けられない人に多い原因のひとつです。
特に高かったモノ、思い出のモノ、もらい物などは、感情や罪悪感が邪魔をして整理が進みにくくなります。
この記事では、整理収納アドバイザーが実際のサポート経験をもとに、手放せないモノに向き合う判断のポイントを解説。
「使っているかどうか」というシンプルな基準で整理する方法、保留ボックスの活用、思い入れの少ないモノから判断練習を始めるステップなど、実践的なコツをご紹介します。
判断できない自分を責める必要はありません。少しずつ「自分にとって必要なモノ」を見極める力を育てていけば、片付けは必ず前に進みます。
お片付けコラム · 2025/05/05
片付け迷子を卒業!汚部屋化を招くNGパターン3つと、リセットしやすい仕組みづくりを整理収納アドバイザーが解説します。
「片付けたいのに、どこから始めたらいいかわからない…」そんなお悩みはありませんか?
本記事では、汚部屋化を招く片付けのNGパターン3つと、その対策を解説します。
SNSの収納術やとりあえずの収納グッズ購入がうまくいかない理由や、リバウンドしない片付けの正しい順番もご紹介。ポイントは「どこで何をしているか」を把握すること=ゾーニング。自分や家族の暮らしに合った仕組みをつくれば、散らかってもすぐリセットできる快適空間が実現しますよ。